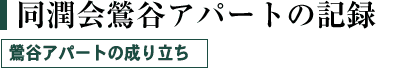|
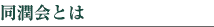 |
|
同潤会は、関東大震災の被災に対して各地から寄せられた義捐金を基にして、1924(大正13)年に設立された財団法人です。震災で失われた住宅の供給と、それに付随した福祉施設の建設と運営という2つの柱をもって、東京と横浜の復興を担うものでした。主として住宅建設の事業を進め、震災直後の仮設住宅や賃貸の長屋から始まり、戸建木造住宅やコンクリートのアパートメントを建設し、また不良住宅地区の改良事業といった都市計画事業など幅広く活動しました。中でも近代的設備を備えたアパートメント事業は有名です。
その後、時代が戦時体制へと移る中、軍事産業に従事する人々のための住宅供給を目的とした住宅営団が設立されました。同潤会は1941(昭和16)年に解散し、すべての事業を住宅営団に引き継ぎました。
|
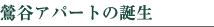 |
|
同潤会アパートは、1926(昭和元)年の中之郷アパートから1934(昭和9)年の江戸川アパートまで計16か所つくられました。そのうち都内(当時は東京市)は14か所です。
鶯谷アパートは、日暮里土地整理事業の終了した当該地を、1927(昭和2)年8月12日に用地買収して、翌々年の1929(昭和4)年3月28日に竣工。同潤会のアパート建設目標2000戸を達成した後に建てられたため、被災者への住宅供給という当初の目標を離れて、より新しい試みを取り入れたものになっています。
|
|
 |
|