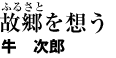|
このエッセイの文字数が千字に限定されているのがいかにも残念である。あれも書きたい、これも書きたいとなったら枚挙に遑がない。浅草生まれではあるが、戦災以来、中学を卒業するまでは、日暮里四丁目に住んでいた。
同潤会アパートは確か三丁目ではなかったか。丁目に拘泥するのには理由がある。お祭りの時期が違うのだ。三丁目は鶯谷の近くにあった三島神社(三島さま)の氏子で、春が祭りだが、私の住んでいた四丁目は、お諏訪神社(おすわさま)で夏の暑い盛りの八月が祭礼だったからで、山車を曳いたり、樽御輿(たるみこし)をかついだりした。樽御輿というのは、本物の御輿が戦災で焼失してしまったので、酒樽に砂を詰めて、荒縄や渋団扇で鳳凰を作り、それを子供たちが夢中でかつぎ廻ったのだ。
戦後で物資(もの)は何もなかったが、子供たちの心は田園的に豊かで、創意工夫に長(た)けていた。神社は異なったが、小学校は三、四丁目とも同じで第二日暮里小学校であった。
改正道路と、日暮里駅から三輪(みのわ)方面に伸びている道路の交叉した角にあった。斜め向いには、当時、財閥解体で三菱を名乗れなかった千代田銀行があった。殆どの子供たちが下駄を履いて登校していた。プールがあって、夏にはそこで泳いだが、男子は全員が六尺褌であった。現在では浜辺でも六尺褌は駄目なのだというが、そんなのはベラボーめである。褌の締め方を知らない奴の戯言(たわごと)に違いねえ。
|