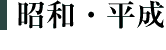 |
|
1927
|
(昭和 2)
|
日暮里地区の下水道工事が竣工
|
|
1929
|
(昭和 4)
|
同潤会三ノ輪アパート竣工
同潤会鶯谷アパート竣工 |
|
1930
|
(昭和 5)
|
都道環状第4号線(道灌山通り)完成
|
|
1931
|
(昭和 6)
|
荒川放水路完成/満州事変起こる
京成電気軌道(株)(京成電車、のち京成電鉄)、日暮里─青砥間開業/日暮里駅開設 |
|
1932
|
(昭和 7)
|
尾竹橋通り開通・市郡合併により荒川区誕生
|
|
1933
|
(昭和 8)
|
京成電車日暮里─上野公園間が開通
この頃鶯谷アパート前の音無川が暗渠になる |
|
1934
|
(昭和 9)
|
尾竹橋架橋
|
|
1935
|
(昭和 10)
|
御隠殿前のお大石橋等が取り払われる
|
|
1936
|
(昭和 11)
|
二・二六事件起きる
|
|
1939
|
(昭和 14)
|
第二次世界大戦始まる
|
|
1940
|
(昭和 15)
|
区内の町会・隣組組織が整備される
切符による生活物資の配給が始まる |
|
1941
|
(昭和 16)
|
太平洋戦争勃発
|
|
1942
|
(昭和 17)
|
市電気局(のちの都交通局)の交通調整により王子電車は市電となる
衣料切符制が実施される |
|
1943
|
(昭和 18)
|
区内各戸で防空壕がつくられる・東京都制施行
|
|
1944
|
(昭和 19)
|
区内建物の強制疎開が始まる(日暮里町2万8320坪)
区内児童の福島県への学童集団疎開が始まる |
|
1945
|
(昭和 20)
|
東京大空襲。区内死傷者600人超/終戦
|
|
1946
|
(昭和 21)
|
日本国憲法が公布される
日暮里駅前大通り(新道放射11号線)が都市計画として決定し整備される |
|
1951
|
(昭和 26)
|
戦災復興区画整理34地区(現・東日暮里5丁目含む地区)の事業認可
鶯谷アパートを分譲 |
|
1953
|
(昭和 28)
|
NHKテレビ放送始まる
|
|
1962
|
(昭和 37)
|
三河島駅構内で二重衝突事故
|
|
1963
|
(昭和 38)
|
日暮里大火(4月、現・東日暮里3丁目の寝具店より出火。5098平方メートルを焼失)
|
|
|





