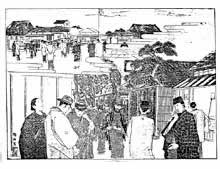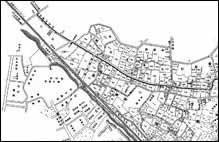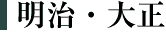 |
|
1868
|
(慶応 4)
|
江戸を東京と改称し、東京府を設置
|
|
|
(明治 元)
|
金杉村は荒川の村むらとともに東京府に編入(小塚原町・中村町を除く)
|
|
1871
|
(明治 4)
|
戸籍法が定められる。廃藩置県
|
|
1872
|
(明治 5)
|
太陽暦が採用され、 明治5年12月3日を6年1月1日とする
|
|
1874
|
(明治 7)
|
金杉村西蔵院内に公立根岸小学校が開校
(学区…金杉・谷中・三ノ輪・谷中本・三河島・ 町屋・下尾久・上尾久) |
|
1878
|
(明治 11)
|
郡区町村編制法により、金杉村は東京府北豊島郡に編入される
|
|
1883
|
(明治 16)
|
日本鉄道会社、上野─熊谷間の営業を開始
|
|
1885
|
(明治 18)
|
日暮里村に公立日暮小学校が開校
(学区…日暮里・谷中本・谷中) |
|
1889
|
(明治 22)
|
市制・町村制により、金杉村は谷中本村、日暮里村と合併して、日暮里村となる
町村制施行のため、金杉村は日暮小学校の学区になる |
|
1894
|
(明治 27)
|
日清戦争
|
|
1896
|
(明治 29)
|
2度の台風襲来により、 荒川・利根川・多摩川出水
|
|
1904
|
(明治 37)
|
日露戦争
|
|
1905
|
(明治 38)
|
第一区線(東北線)と土浦線を結ぶ日暮里─三河島間が開通。日暮里駅が開設される
|
|
1906
|
(明治 39)
|
東京電燈(株)、千住発電所完成
|
|
1907
|
(明治 40)
|
連日の大雨で荒川など洪水発生
|
|
1908
|
(明治 41)
|
明治期最大の洪水発生。関東一円被害甚大
|
|
1911
|
(明治 44)
|
荒川放水路事業が起工
|
|
1912
|
(大正 元)
|
国道第4号線(下谷通り)の工事着工
|
|
1913
|
(大正 2)
|
王子電気軌道(株)、 三ノ輪─飛鳥山下間の営業開始
日暮里村に町制施行、日暮里町となる |
|
1914
|
(大正 3)
|
第一次世界大戦
|
|
1918
|
(大正 7)
|
米価が沸騰し、米騒動が起きる
|
|
1921
|
(大正 10)
|
市電、東京駅─三ノ輪橋間が開通
|
|
1922
|
(大正 11)
|
東京市最初の下水処理場が三河島に完成
|
|
1923
|
(大正 12)
|
関東大震災
|
|
1925
|
(大正 14)
|
日暮里大火(3月、 金杉より出火、 約2000戸を焼失)
日暮里土地整理組合が設立 尾久に同潤会住宅73戸が建設される 治安維持法が公布・施行 |
|
1926
|
(大正 15)
|
日暮里土地整理事業が竣工
|