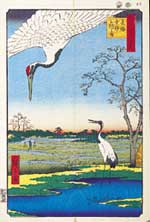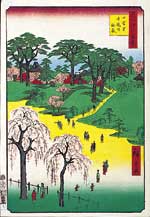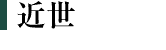 |
|
1600
|
(慶長 5)
|
関ヶ原の合戦
|
|
1603
|
(慶長 8)
|
家康が征夷大将軍になり、江戸幕府成立
|
|
1625
|
(寛永 2)
|
寛永寺が建立される
|
|
1628
|
(寛永 5)
|
江戸近郊に鷹場が置かれる
|
|
1639
|
(寛永 16)
|
鎖国
|
|
1646
|
(正保 3)
|
金杉村(現・東日暮里あたり)ほか5カ村が東叡山領となる
|
|
1657
|
(明暦 3)
|
明暦の大火
|
|
1685
|
(貞享 2)
|
生類憐れみの令が制定される
|
|
1704
|
(宝永 元)
|
御隠殿が幕府から宮家に渡される
|
|
1707
|
(宝永 4)
|
富士山が大噴火し、宝永山ができる
|
|
1716
|
(享保 元)
|
享保の改革
|
|
1725
|
(享保 10)
|
青山久保町から出火して、金杉、下谷、谷中まで焼失する
|
|
1753
|
(宝暦 3)
|
金杉村杉苗の畑地が御隠殿の地になる
|
|

|