ターボ期の終焉
|

1986年RA166E(BB7)
1.494cc 80度 V6
1000ph/11.600rpm
16戦9勝 |
←このエンジンをベースにウイリアムズ→ロータス→マクラーレン、と供給して
勝ち続けたが、勝利がHONDAに偏りF1界のバランス維持を保てなくなる事
(スポンサーの一定チーム集中や楽しさの減少)が懸念され
89’にターボ禁止になってHONDAは休止を提案した
休止を提案した理由
・レースマネージメントに於けるエンジンの技術的貢献度の割合が減って(下左右図)
エンジン開発のやりがいが無くなる。
・10年を区切りにこれまでの目的は一応達成した。 |
|
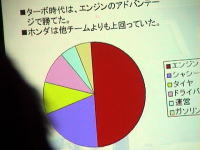
ターボエンジンでのレースに於ける
エンジン重要度の占める割合(赤部分)
|
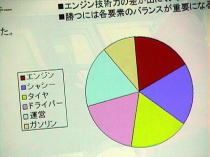
NAエンジンでは他の要素の割合と変わらなくなり、エンジンの性能だけでは勝利に繋がらない。 |
|
しかし、
休止を提案された本田宗一郎氏曰く、
『ターボ禁止はウチだけか?』
「いえ、全チームです。」
『ならばいいじゃないか、
同じ条件で戦ってこそ
初めてヨーロッパの人からも
尊敬を受けることが出来る。』
そう言われ、皆納得した。 |
 |
NAエンジンの開発Ⅰ
|

RA-109E
72度V10
ボア 91mm
ストローク 53.7mm
重量 173、4kg
出力660/12.000 |
NAエンジンのコンセプト
ステップⅠ
軽量、小型、高出力のバランスとして
V10を選択。自動MTの開発。
ステップⅡ
夢の12気筒
アクティヴサスペンション
空力のサーキットシミュレーションの熟成
ステップⅢ
究極のV12『飛躍型』エンジン
V10より小型、軽量且つ高出力 |
NA元年になって他チームとの差が殆ど無くなりトータルバランスと信頼性が勝利のカギを握る、と判断して
軽量、小型、高出力のエンジン開発が
目標とされた。
*本田技研で車体と空力の研究開始
*本田技研でセミオートマ着手
*本田技研でアクティヴサスペンション開発
*無限でテストチーム結成 |
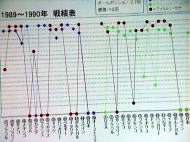
戦績は必ず1位か2位を獲得、
しかしこれではダメ
勝たなくしては目標達成にはならない
|
・シリンダーブロックをアルミに変更
・バンク角を72度に変更
・ベルトからギア駆動へ変更
課題
・新燃料の開発
・燃費改善
・出力、燃費、エンジン耐久性の向上
・車体の更なる進化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAエンジンの開発Ⅱ・
V12エンジンへのステップ |
V12の利点として
吸気の開口面積を広げる事で高回転化が可能。
(吸気が一定の速度を越えると乱流で空気が十分入って来ない)
開口面積を大きくして吸気を上げる事で、計算上馬力が約10%程UPする。
(700ph→770ph)
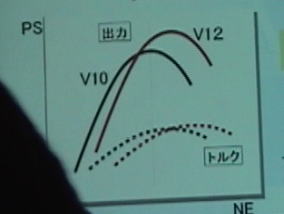 |

RA121E
1991V12エンジンを投入
RA121E
60度V12
ボア 86.5mm
ストローク 49.6mm
重量 157.6kg
出力 765ps/13.600 |
V12エンジンの特徴
1:基本スタート
信頼性の確保
2:低燃費、低フリクション
第3戦サンマリノから吸気系改善
3:高回転、高出力
第7戦仏GPから軽量化
4:高回転・高トルク
8戦の英GPからボア変更
85から86,5へ
第11戦ベルギーGPから可変吸気官長システム採用 |
|
課題
車体の空力、シャーシの性能UP
新骨格+PVRSエンジンの早期投入
セミAT/アクティヴサスの早期成熟、ニューシャーシへのリンク
*こうしたレース毎に段階的な開発を進め、スペック3とか4と呼んだ呼称が現在のF1でも各チームでも使われるようになった。
|
|
休止宣言
最後のレースエンジン究極のV12を目指して
|
91年の問題と課題
* 初のV12エンジンと新シャーシのマッチングが十分でなく
* ウイリアムズに対してエア路ダイナミックスのアドバンテージが無かった
*エンジン重量が他社の水準より10kg以上も重く、車トータルでの戦闘力が下がってしまった
V10の技術でV12を作るのは無理がある
重量、重心が車体に合っていないのではないか
飛躍した究極のV12の製作を目指す
エンジン戦略構想
コンセプト
車体
・エアロダイナミックスの改良を第一優先とする
・車体剛性をより向上させる
・冷却効率向上を計る
・車体知能化
エンジン
・軽量コンパクトV75度構造
・高出力高回転PVRS動弁系を採用する |
目標
6%向上
5%向上
2%向上
セミATアクティヴサスの採用
重量10Kg減
高さ50mm減
出力:20~30ph増 |
|
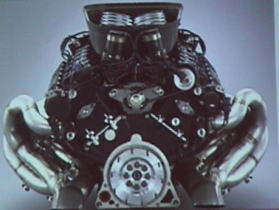 |
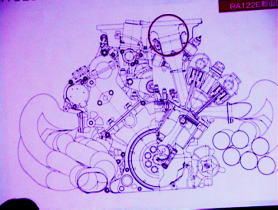
設計図 |
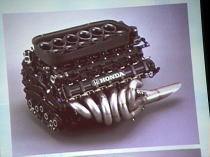 |
飛躍型V12エンジン
コンセプト
高回転:75度バンク
超軽量化
前年比5kg減
高出力(前年比約20phアップ)
エアロダイナミックスエンジン(全高ダウン)
フライバイワイアーシステム投入
可変吸気官長の継続投入
燃料開発
車体領域
自動制御トランスミッション
アクティヴサスペンション
|
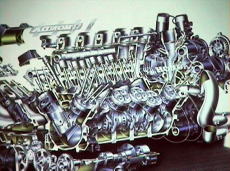
『金属でありながら生物のようなエンジンでした。』(透過図) |
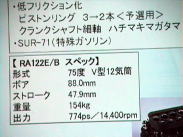
『技術でやりぬいたエンジン』といえる |
後編へ |

